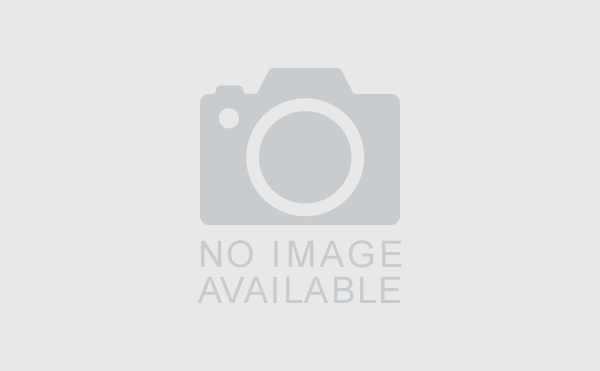岡井仁子さんの思い出(宮崎日日新聞記者 甲斐亮児)
「強い母親」との出会い
私と岡井仁子さんの出会いは2008年4月でした。当時私は、岡井さんが陶芸工房を構えていた宮崎県国富町を取材エリアとする宮崎日日新聞東諸(ひがしもろ)支局に赴任したばかりでした。「大韓航空機撃墜事件で犠牲になった長男夫婦を追悼するコンサートを開くので、取材をお願いしたい」。そんな電話が最初でした。
支局に赴任する前、事前の学習のため、前任者の記事におおまかですが目を通していました。岡井さんの名前もその中にありました。初めてお会いした印象は「強い母親」。穏やかな口調と、対照的な目力の強さに圧倒されました。
取材を進めるなかで、途方もない悲しみと、事件を風化させないという強い意志を知りました。それから、岡井さんの記事を書き続けました。記者コラムでも折に触れて取り上げました。正直に言えば、宮崎県民にとって撃墜事件は遠い出来事でした。「このような人がいること、そして事件のことを知ってほしい」。そんな思いがありました。
記事が掲載されると岡井さんからお礼の電話が来ることがありました。支局は同じ国富町内にあるとはいえ、他の取材もあり、工房にはなかなか行けません。近況を聞くのが楽しみでした。
始まった挑戦、広がる輪
この年の末、私は岡井さんから大きな計画を打ち明けられます。撃墜現場に近いサハリンのネベリスクで「野焼き」を行うことです。「サハリン・プロジェクト」。そう名付けていました。私はサハリンの事情には疎く、細かいことは分かりませんでしたが、「大変そうだな」と感じたのを覚えています。サハリン側のコーディネーターはサハリンの有力紙「自由サハリン」のミハイル・ブガーエフさんでした。
岡井さんは「サハリン・プロジェクト」の一環で、野焼きに先立ち、2009年9月にサハリン州美術館で陶芸の個展を開きました。個展の準備を手伝うため、ブガーエフさんの紹介で、サハリン在住の画家ナタリア・キリューヒナさんが2009年5月下旬に国富町を訪れ、岡井さんの工房に1カ月半滞在して陶芸の手ほどきを受けるとともに、国富の風景を絵にしました。私はキリューヒナさんが国富を離れる前に町内で開いた個展を取材する機会を得ました。年が変わり、2010年2月にはブガーエフさんが野焼きの打ち合わせで国富町を訪れ、町役場に町長を訪ねて挨拶した際に取材しました。
遠く離れたロシアの人と接したのは初めてでした。取材を通して二人と話すことができたのは得がたい経験でした。さらに、岡井さんの取り組みを取材に訪れた中央大学の女子学生も取材しました。優しい目で事件のことを語る姿を覚えています。
国富町の「トトロの森」の工房で野焼きの作品を制作する岡井仁子さん=2011年7月6日

岡井さんの挑戦を紙面で応援しようと、2010年7月初め、岡井さんを紹介する3回の連載記事「鎮魂の『野焼き』 サハリンへ」を書きました。反響があったかどうかは分かりません。ただ、岡井さんのところには多くの人たちが集まってきました。国富町民にも応援する人たちが現れ、町当局を巻き込んだ事業になりました。
悲痛な決意「それでもやる」
プロジェクトは順調に進んでいるように思えました。そんなある日、岡井さんから切羽詰まった声で電話がありました。「野焼きができなくなるかもしれません」。記憶では確か、ロシア側から「追悼を前面に出すのであれば受け入れられない」と連絡があったということでした。「事件のことは口にするな」と言うに等しい非情な宣告です。私は憤りました。一地方紙記者の私にできることはありません。関係者のみなさんの尽力で、何とか実現に向かうことを祈るばかりでした。
しばらくして、「ネベリスク市がロシアと日本の文化交流行事として主催し、日本からの代表団が野焼きを手伝う枠組みでどうか」とロシア側から提案があったと岡井さんから電話がありました。
岡井さんは「それでもいいからやる。後には引けない」と言い切りました。たとえ事件のことは話せなくても、子を亡くした親の思いはきっと伝わるはず。そんな気持ちが伝わってきました。
8月末、共同通信の配信記事で、野焼きが無事に行われたことを知りました。実現を喜ぶ半面、岡井さんの胸中を思うと複雑でした。
サハリン2回目の野焼きで作品を仕上げた岡井さん=2011年8月21日、ネベリスク

聞いておきたかった言葉
その後、私は異動で内勤になり、取材に出ることはなくなりました。岡井さんのことは後任者の記事で読み、頑張って活動を続けていることに安堵していました。脳出血で倒れ、右半身が不随になった後も「左手だけでも創作はできる」と話していたそうです。そして、2020年8月、岡井さんの訃報に接しました。「もう会えないのだな」という寂しさと「もっと話を聞いておけばよかった」という悔しさがありました。
岡井さんは「遺族」としての顔に焦点が当たりがちですが、優れた陶芸家でもありました。本紙の美術論評にも岡井さんの個展が数回登場し、斬新さが高く評価されていました。岡井さんの芸術論も聞いてみたかったと思います。
思い出の器、そして今
以上が、私の岡井さんの思い出のすべてです。まだ小さかった娘を連れて、岡井さんの作陶教室に参加したことがあります。岡井さんに手伝ってもらいながら作った小さな器は時々、我が家の食卓に並びます。たあいない話かもしれませんが、岡井さんが娘の名前を聞いて「私の行きつけのブティックと同じ名前ね」と笑った顔が思い出されます。
岡井さんの作陶教室で筆者と筆者の娘が作った器

器を見るたび考えます。岡井さんは天国で長男夫婦と再会し、「お母さんは頑張ったのよ」と語りかけただろう、と。そして、平和を願い続けた岡井さんが今の世界を見たらどう思うだろうか、と。
私は岡井さんのことを、そして事件のことを忘れません。それが岡井さんへの何よりの手向けになるからです。
2025年9月1日 宮崎にて