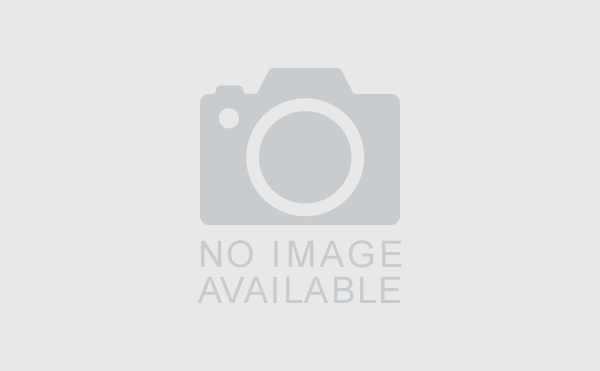母の愛、そして「悲しみの十字架」(元MRT宮崎放送ディレクター 温谷禎康=ぬくたに・よしやす)
私が岡井仁子さんのことを初めて知ったのは勤務していたMRT宮崎放送の駆け出しのディレクター時代、先輩ディレクターが作った大韓航空機撃墜事件の追悼番組を見た時である。岡井さんは長男の真さんを事件で亡くし、当時、宮崎県国富町に陶芸窯を構えていた。番組は「事件を風化させてはならない」と活動する岡井さんの姿を丹念に追った。多くの民間人が乗る大韓航空機が「領空侵犯」を理由にソビエトの戦闘機に撃墜され、全員死亡した惨劇に、胸を締めつけられた。
番組のBGMに使われていたのが、真さんがアメリカのバークリー音楽大学に留学中に作曲した「“F”」だった。ギターの音色はどこか物悲しく、印象的で、耳に残った。
サハリンへの同行取材決まる
2010年、知り合いの陶芸家から、岡井さんが事件現場のサハリンに渡り「追悼の野焼き」を行うから同行してみてはどうかと連絡をもらった。これまでの岡井さんらの熱心な活動が、墜落地点に一番近いネベリスク市の市長の心を動かしたのだ。
取材のため、ひっそりとした森の中に佇む陶芸窯で初めてお会いした岡井さんは、笑顔が素敵で、おしゃれで、活発で、とてもエネルギッシュな女性に見えた。リビング横の部屋には、真さんの楽曲の楽譜などの遺品のほか、小さい頃に描いた絵なども捨てずに残してあり、岡井さんは時折、その部屋で真さんを想いながら時間を過ごすことがあるとおっしゃった。私はその言葉を聞き、事件を風化させないために長年活動する岡井さんに寄り添いたいと強く思った。
サハリン初の野焼きの準備風景を撮影する筆者(右端)=2010年8月27日、ネベリスク

岡井さんにサハリンへの同行取材を許された私は、取材を一から始めるにあたり資料を集めることにした。大韓航空機撃墜事件が起きた1983年9月当時、私は9歳で、正直、事件の記憶も定かではなかったからである。撮影が始まり、岡井さんが事件や真さんについて話す言葉に胸が熱くなった。
事件当時は福岡に住んでいて、事件の一報が入った朝、報道陣が自宅に集まってきたこと。その後、「大韓航空機はサハリンに強制着陸。乗客・乗員は全員無事」との情報が入り、安堵して記者たちと皆でビールで乾杯したこと。そして、ソビエトの戦闘機に撃墜された事実を突きつけられたこと…。岡井さんは一つ一つ、昨日のことのように詳しく話してくれた。
困難乗り越え現地へ
2010年の8月初めだった。サハリンでの野焼きまであと3週間となり、準備が最終段階を迎えたとき、ロシア側から「野焼きと大韓航空機事件の追悼を結びつけないでほしい」との条件が突如課せられた。犠牲者の追悼のための野焼きを福岡や稚内で続けてきた岡井さんは衝撃を受けた。ロシア側の手紙を受け取ったときは頭に血が上ったが、「心の中で追悼すればよい」とサハリン行きを決断した。
点火直後、少しずつ大きくなる野焼きの炎=2010年8月27日

稚内からフェリーの定期便でサハリンへ向かったのは私を含め20人。事件発生当時から岡井さんを支える支援者、北海道内の地方議員の方々、そして宮崎の陶芸教室のお弟子さんたちである。私はディレクター兼カメラマンで、海外ロケには心細い一人体制だった。
入港したのはサハリンのコルサコフ。正直、ソビエト、ロシアへの負のイメージを払拭できず、銃を掲げて厳重な警備を行う入国審査にとても緊張したのを覚えている。
コルサコフから、車に乗り換えて州都ユジノサハリンスクへ向かい、ホテルに一泊。翌日、山を越えて現地ネベリスクに着いた。舗装されていないところが多く、土煙が舞う悪路だった。日露戦争のあと、日本占領時代の樺太(サハリン)の地図を見ると、コルサコフは大泊、ユジノサハリンスクは豊原、ネベリスクは本斗という表記になっている。樺太と呼ばれていたサハリンはとても遠い存在と思っていたが、馴染みのある漢字の地名に不思議な感覚を覚えた。
岡井仁子さんの野焼き作品「悲しみの十字架」=2010年8月29日

心の中で追悼 平和祈る
野焼き会場は2007年のサハリン西方沖地震により海岸が隆起してできた土地で、かなりの広さがあった。野焼きの準備のために多くのロシア人が集まり、岡井さんの写真が掲げられていた。ロシア語のため読めなかったが、「日本人の陶芸家 岡井仁子」と紹介されているということだった。
岡井さんの友人でサハリンに住む画家のナタリア・キリューヒナさんの協力で、地元の子どもたちも野焼き用の作品を制作した。皆、思い思いの作品を野焼きの薪の中に置き、その上に多くの材木を重ねて野焼きのベースを作った。
「悲しみの十字架」を持つ岡井さんを撮影する筆者(中央)=2010年8月29日

夕方になると、特設ステージでは若者たちによるコンサートが始まり、イベントは盛り上がってきた。岡井さんは「日本から有名な陶芸家が参加してくれました」とマイクで紹介され、来賓のサハリン州の有力者たちと松明を灯し、野焼きに点火した。材木が生乾きで初めはくすぶったが、火はパチパチと燃えて次第に大きくなり、やがて空へ昇る大きな炎となった。
夜がふけても続く若者たちのロックの演奏を背に、岡井さんと会場をこっそり抜け出し、海辺へ向かった。大韓航空機が墜落したとされるモネロン島(海馬島)の方へ流れていくよう灯籠を持ってきたのだ。ロウソクに火をつけ、私たちは心の中で犠牲者を悼み、平和を祈った。
野焼きを終え、岡井さんを取材する中央大学の学生(左)と筆者=2010年8月29日

岡井さんがロシアのサハリンの地で焼いた作品は「悲しみの十字架」。犠牲者の無念や遺族の悲しみ、平和への思いを込めた渾身の作品である。
東西冷戦下のサハリンで、なんの罪もない人たちが乗った民間機が撃ち落とされた。長い年月が経った今でも、事件の真相が解明されたとはいえない。
野焼きを終え、岡井さんがインタビューに答えた。
「私は子どもを守れなかった。子どもの命を守ることができなかった」
岡井さんが逝って5年、母としての一言を今も忘れられない。
2025年9月1日 岡井仁子さんを偲んで
大韓機が沈んだモネロン島の島影を探す筆者=2010年8月29日