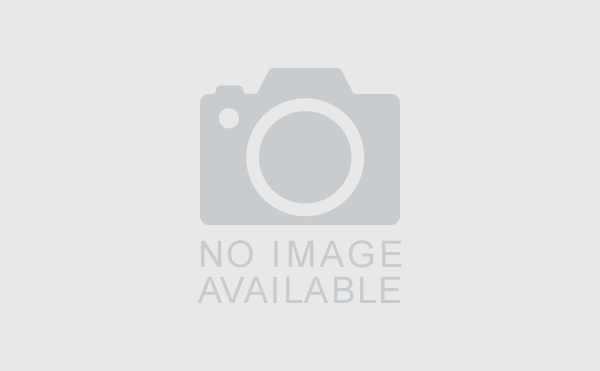大韓航空機撃墜事件40年(元北海道新聞編集委員 山本肇さん)
亡き息子に捧ぐ「祈りの火」 いつか真相の扉こじ開ける
福岡から訪ねて来た女性は「遺族会」の名刺を差し出し、「息子たちの最期の様子を知りたい」と切り出した。
一九九一年四月初めの昼下がり。
名刺には「大韓航空機撃墜事故(事件)遺族会 岡井仁子」とある。
当時、北海道新聞東京支社政治経済部で日ソ関係を担当していて取材拠点にしていた永田町の国会記者会館で一時間ほど面談した。この出会いがきっかけで、サハリン(樺太)に何度となく一緒に渡り、「祈りの火」を灯すことになる。

※岡井仁子さんはサハリン初の野焼き作品を「悲しみの十字架」と名づけた。
表情に安堵感が漂う=2010年8月29日、ネベリスク
東西冷戦下の一九八三年九月一日未明、ニューヨーク発アンカレジ経由ソウル行きの大韓航空007便が領空を侵犯したとして、サハリン上空でソ連の軍用機に撃墜された。機体はサハリン南西沖に沈み、日本人二十八人、在日韓国人一人を含む乗客と乗員合わせて二百六十九人全員が犠牲になった。日本とソ連の捜索によっても誰一人帰ることはなかった。事件から四十年たっても、遺体がどうなったのかは謎のままだ。遺族は肉親の不条理な死を受け止められないまま、一人また一人と鬼籍に入る。冷戦終結から三十五年。米中ロの三国が覇権を競う世界は新たな軍事的緊張を生み、ウクライナ、パレスチナで上がった戦火はいつやむとも知れぬ。民間機が巻き込まれる事件が今後また起きない保証はない。事件を風化させてはならない。そして、いつの日か、真相の扉をこじ開けたい。
---
一九九一年二月、サハリンに出張し、007便の墜落現場に近いネベリスクのイワン・マラホフ市長にインタビューした。彼は事件直後、海軍で捜索の指揮を執ったと言い、「乗客らの遺体の一部を回収したが、ばらばらで、わずかだった。日本側に引き渡されたと聞いている」と証言した。ソ連の幹部が遺体回収を認めるのは初めてだった。
現地の漁業無線局から電話口で読み上げて送った原稿は翌日朝刊の一面トップを飾った。マラホフ氏が言ったような日本側への遺体引き渡しの事実はないが、遺体に関する描写は具体的で、信用できると確信した。
「特ダネ」は西日本新聞や東京新聞にも載り、記事を読んだ岡井仁子さんが福岡から訪ねてきた。岡井さんは長男の真さん=当時二十二歳=を大韓航空機撃墜事件で奪われた。真さんは高校を卒業後、米国ボストンのバークリー音楽大学に進んでジャズとギターを学び、卒業して帰国する途中だった。新婚の妻葉子さん=当時二十五歳=が一緒だった。事件に関する情報は乏しく、岡井さんら遺族が現地を訪問できたのは事件から六年後の一九八九年、ペレストロイカ(改革)を進めて後に大統領となるゴルバチョフ氏が登場してからだ。
悲しみを土にぶつける
岡井さんは和歌山県那智勝浦町で生まれ、製紙会社勤務の亨さんと結婚後、新婚時代を送った北海道の釧路で真さんを授かった。事件当時は福岡で暮らしており、趣味で始めた陶芸に本格的に取り組むようになる。やり場のない悲しみや怒り、悔しさを土にぶつけた。「公募展で入賞すれば『大韓航空機撃墜事件で息子を亡くした母親』と報道される。事件を忘れずにいてもらえる」と思った。
やがて、宮崎県国富町を終のすみかと決め、工房を構えた。工房にはさまざまな作品が並ぶ。「珠うしお」と名づけた作品がある。掌中の珠、最愛の子どもを失った悲しみを張り裂けた壺で表した。迫力に圧倒される。
創作活動のかたわら、「野焼き」に取り組んだ。古代、縄文土器の焼成法に倣い、丸太や木片を組み上げた「窯」に火を放ち、器を焼き上げるのだ。長きにわたって争いがなかった縄文時代のような平和な時代が訪れるようにとの願いを込めた。「迎え火」の意味もある。一九八九年十一月、福岡県の夜須高原で初挑戦したのに続き、一九九一年から事件現場に近い稚内、翌九二年から007便の機体の一部や遺留品が流れ着いた紋別で手掛けるようになった。

※画家のナタリア・キリューヒナさん(左)らと野焼きの炎の前に立つ岡井さん(中央)
キリューヒナさんは2009年、岡井さんの工房に長期滞在して陶芸を学び、サハリンの個展をサポートした=2011年8月19日、ネベリスク
悲劇繰り返す恐れも
007便はなぜ航路を大きく外れてサハリン上空に迷い込んだのか。国際民間航空機関(ICAO)は九三年九月、ブラックボックスの解析結果などから自動操縦装置の操作ミスと断定したが、岡井さんら遺族は単なる操作ミスとは信じられなかった。現場周辺にはソ連の軍事施設が集中し、米軍の偵察機による領空侵犯が常態化していた。自衛隊と米軍は007便の領空侵犯を把握し、「(ミサイル)発射完了」「目標撃破」など撃墜に至るソ連軍の通信記録を共有していながら、なんら対応しなかった。日米の探知能力をソ連に知られるのを恐れたからにほかならない。岡井さんは「事件の後ろに米国がいるのではないか」との疑いを最後まで捨てきれなかった。
同様の事件が二〇一四年七月、ウクライナ東部であった。マレーシア航空の旅客機がロシア製ミサイルで撃墜され、乗客・乗員二百九十八人全員が亡くなったのだ。現場は親ロシア派勢力が支配する地域。合同捜査チームは昨年二月、ロシアのプーチン大統領が親ロ派勢力への地対空ミサイル提供を決めた可能性が高いとの捜査結果を公表した。近年、航法システムの性能が高まったとはいえ、ウクライナ侵攻に象徴される世界情勢を見れば、同様の悲劇が起きる可能性は決して低くない。
現地の人々の共感広げる
岡井さんとは二〇〇八年から十五年にかけて、サハリンに六回渡った。最初の渡航は事件から四半世紀たった二〇〇八年七月。稚内とコルサコフを結ぶ定期フェリーでサハリンに渡り、事件直後に捜索に携わった漁船の船長ら関係者に乗客の遺体回収、埋葬の有無を尋ねたが、空振りに終わった。帰りのフェリーで話し合い、「来年はサハリンで個展を開こう」と決めた。
「『遺族です』と正面から迫っても、真相の扉は開けられそうにない。文化交流を進めることで情報をたぐり寄せていけるのではないか」と考え直したのだ。翌〇九年九月、サハリンの美術協会と在ユジノサハリンスク日本総領事館の力添えを得てサハリン州美術館で個展を開き、代表作の「珠うしお」など十点を展示した。
「珠うしお」にロシア語でこんな説明を付けた。
「私たちは文字通り『掌中の珠』を失った悲しみと苦しみを背負いながら、せめてどこに沈んでいるのかだけでも知りたいと念じつつ、毎日を過ごしています」
来場者は作品の数々と説明を交互に見つめては、うなずき、時に涙を流した。岡井さんが通訳と二人で席を外している時に美術協会の女性が来場し、麦わら帽子を五つ配した作品の説明を求めた。事件の影すらなかったころ、家族五人で過ごした夏をモチーフにした作品で、題名は「Recollection」。女性が帽子の数の意味を聞くので、「岡井さんは五人家族でした」と、つたないロシア語で答えると、女性は納得した様子で、間もなく戻ってきた岡井さんと肩を抱き合った。
事件に関する報道がソ連時代から皆無に等しいロシアで、市民の理解が少しとはいえ得られたのは大きな成果だった。

※サハリン州美術館で個展を準備する岡井さん。
麦わら帽子の作品が「Recollection」、左端は「海ざくろ」=2009年9月4日
交渉半年、野焼き実現
翌二〇一〇年八月、サハリン初の野焼きをネベリスクの海岸で決行した。ネベリスク市との交渉に半年を費やし、最後はウラジーミル・パク市長が「慰霊」を前面に出さない条件で、日ロの文化交流事業として許可する英断を下した。日本から遺族ら二十人が同行し、点火から「窯出し」までの三日間で千二百人が訪れた。日ロの作品六十点余りが焼き上がり、岡井さんは自身の作品「悲しみの十字架」をネベリスク市に寄贈した。
野焼きは夏まつりのメインイベントとして定着し、岡井さんが参加してもしなくても市当局が毎年実施していたが、コロナ禍以降、中断したままだ。岡井さんは二〇一九年三月、脳出血が再発し、翌二〇年八月二十九日、帰らぬ人となった。八十四歳だった。

※車椅子で最後にサハリンに渡った帰途、慰霊のために買った赤いバラをフェリーのデッキから海に投じた。
奥は事件で父親を亡くした山口真史さん=2015年8月 19日
サハリンではたくさんの人たちの支援を受けた。日刊紙の副編集長、画家、ネベリスク市の文化担当者、コリアン系のロシア人家族…。家庭に食事に招かれることもあった。
冷戦終結後も地球上で戦火がやむことはない。日本は「戦争ができる国」に向けて突き進む。岡井さんが生きていたら、「これじゃだめよ」と言って、平和のメッセージを発信するために行動を起こしていたに違いない。
取材から始まった大韓航空機撃墜事件は気がつくとライフワークになっていた。どんな困難が立ちはだかっても諦めず前向きな岡井さんと一緒に、いつか真相にたどり着きたいと思った。事件を風化させないため、遺族会の四十代、五十代の若手とともにホームページ開設の準備を進めている。ウクライナ情勢が沈静化して渡航が可能になったら、サハリンに渡り、007便の乗客の手掛かりを得たい。岡井さんがいつも言っていたように、最後のページはまだ閉じられていない。

※ネベリスクを訪ねるたび、岡井さんは遺族会が建てた慰霊碑に向かい手を合わせた。
いつ行っても周りはきれいに整備されていた=2011年8月20日